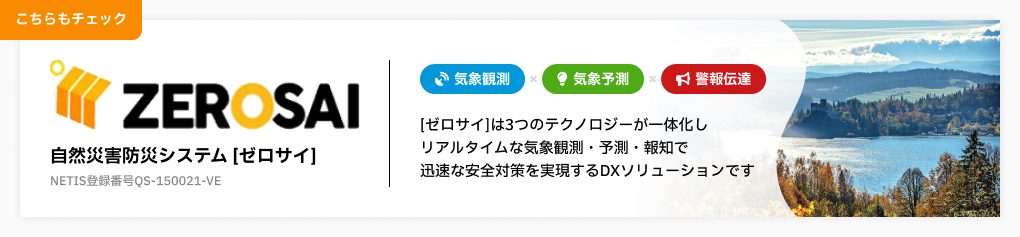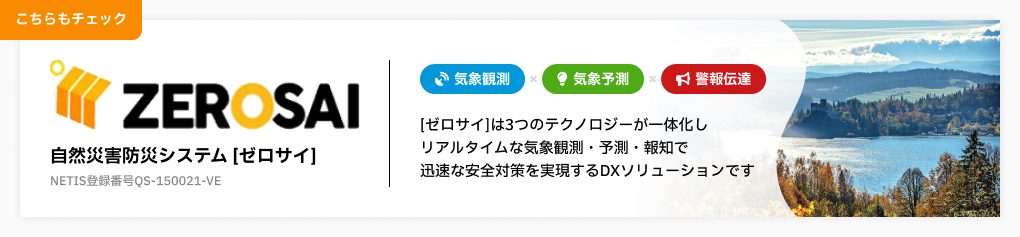2024-02-02
大気の状態を表す用語(雪など)
立春を迎え歴の上では春ということになるのですが。もうしばらく寒い日が続きそうです。
今回は冬の大気の状態を表す用語について紹介していきます。
知ってそうでも、詳しくはどういったものか説明できないという方が多いのではないでしょうか。
【雪】
雪とは :雲の中で水蒸気がくっつきあって氷の粒となり、上昇気流で支えきれないほど
大きな粒となったとき降ってくる氷の結晶。溶けずに降ってきたもの。
出来る条件:日本海側では上空の気温が2~3℃以下、太平洋側では1~2℃以下で雪ができる
と言われています。気温が高いと降ってくる間に溶けて雨になります。
しかし気温がそれほど低くなくても湿度が低ければ雪になる可能性があります。
雪のできる条件は気温と湿度が関係しているということです。
【霙】みぞれ
霙とは :雪と雨が同時に降る現象。雪が空中で溶けかかって雨と混ざって降るもの。
気象庁は「みぞれ」が降った際、雪として記録します。
できる条件:湿度が関係していますが上空の
気温が3℃以上、8℃以下の場合に霙になりやす
いと言われています。

【雹】ひょう
雹とは :直径5mm以上の氷の粒。
できる条件:発達した積乱雲の中で下降と上昇を繰り返し、氷の粒がくっつき合って大きくな
ることによりできます。実は雹は冬以外に降ることが多いです。
理由は地表の気温と上空の気温さが大きい、春・夏・秋に積乱雲が発生しやすい
からです。
【霰】あられ
霰とは :直径5mm未満の氷の粒。
できる条件:雹と同じ。

合わせて【雪が降るかの気温の目安】についての記事もごらんください。
ひょう・あられは冬以外の季節に降ることが多いです。
雪 みぞれ ひょう あられ それぞれの違いは、簡単なので降った時にこれは何かなと考えてみるのも楽しいかもしれません。